第22回 父変える
父変える
●Fall
 “二季”だって?、、、僕は身を持って秋(Fall)を実感してますよ。“あ~っ、また抜け落ちた!(落髪)”、。えっ、そうやない、Fallは“落葉”でしたか。
“二季”だって?、、、僕は身を持って秋(Fall)を実感してますよ。“あ~っ、また抜け落ちた!(落髪)”、。えっ、そうやない、Fallは“落葉”でしたか。
奥山に もみじ踏み分け鳴く鹿の
声聞くときぞ 秋は悲しき
鹿は“恋の季節”かも知れんがその蹄に踏まれる“落葉”はどうやろ。水面に落ちれば“紅葉筏(もみじいかだ)”で、これまた風情があるのだが。
ちはやぶる 神代もきかず竜田川
唐紅に 水くくるとは
初の女性首相誕生に沸く昨今、やたらと奈良や和歌の風味が脳内に浸蝕してくる。「竜田川?、普通の川や」と奈良の義姉は言う。情緒も何もない。まあ、人生も“晩秋”を超えると風流よりも“現実”なのか、この人の場合は“落葉”よりも“落飾”。いや、出家のことではありません、やたらと古着を下さるのだ。今や我が家は不要物の終着駅と化している。堪らず妻がトコロテン式“断捨離”を発動。玉石混淆の山の中から「ええい!」と無造作に袋に詰める。「うんっ?」、と手が止まる。「これ、母の手編みのチョッキちゃうか、何回着たんやろ」と我が身の親不孝に顔が曇る。捨てるのは忍びない。しかし時として決断が必要。かつて糟糠の妻が仕立てた上衣を躊躇なく売った男がいた。
●人身売買
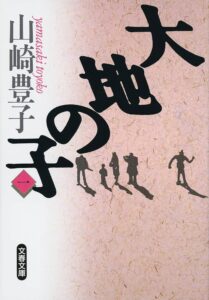 「この子が助かるのなら」と、妻が誂(あつら)えたばかりの綿入れを手放したのだ(山崎豊子著「大地の子」)。男の名は陸徳志、中国残留孤児の物語だ。尤も、小説では“残留”ではなく関東軍に棄てられた“棄民”と描かれている。
「この子が助かるのなら」と、妻が誂(あつら)えたばかりの綿入れを手放したのだ(山崎豊子著「大地の子」)。男の名は陸徳志、中国残留孤児の物語だ。尤も、小説では“残留”ではなく関東軍に棄てられた“棄民”と描かれている。
目の前に屹立する痩身の少年(以降、“一心”(養子となった後の名前)。その哀れな姿に堪らず声を発したのが陸徳志。後にこの一心の義父となる高徳の人。奴隷商人の「金が無えのなら、お前さんのその新品らしい綿入れの上衣を脱ぎねえ」の言に「ならば」と応じたのだ。かくして一心は商人の手から解放された。二人を結び付けた最初の場面であった。
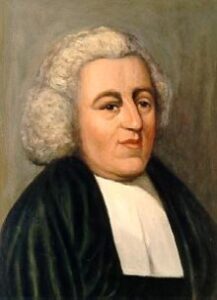 なに、奴隷商人、最低!、と唾棄したくなりますが、かの甘美な讃美歌「アメイジング・グレース」を紡いだジョン・ニュートンも元は奴隷輸送船の船長でした。航行中の船を襲った未曾有の暴風雨、絶体絶命の窮地に思わず口から出た「神様!」の叫び。やがて嵐が去ると、彼は何年も封殺していた神の言葉、聖書を開いていました。キリストを信じるに至ったとき、奴隷を売買していた自分こそが、実は罪の奴隷であったことに気付きます。懲らしめよりも寧ろ“赦し”で罪に気付かせて下さった神の恵みを知り、その驚きを詠ったのがこの賛歌なのです。
なに、奴隷商人、最低!、と唾棄したくなりますが、かの甘美な讃美歌「アメイジング・グレース」を紡いだジョン・ニュートンも元は奴隷輸送船の船長でした。航行中の船を襲った未曾有の暴風雨、絶体絶命の窮地に思わず口から出た「神様!」の叫び。やがて嵐が去ると、彼は何年も封殺していた神の言葉、聖書を開いていました。キリストを信じるに至ったとき、奴隷を売買していた自分こそが、実は罪の奴隷であったことに気付きます。懲らしめよりも寧ろ“赦し”で罪に気付かせて下さった神の恵みを知り、その驚きを詠ったのがこの賛歌なのです。
さて、一心は“綿入れの上衣”という愛の代価で陸徳志に買い取られましたが、神様もまた私達をキリストという尊い代価で買い戻して下さったと聖書は語ります。
「ご承知のように、あなたがたが父祖伝来のむなしい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちる物にはよらず、傷もなく汚れもない小羊のようなキリストの、尊い血によったのです」(Ⅰペテロ1章18節、19節)。
難語「贖い」とは元々の主人に買い戻された、という意味です。無自覚のうちに主人の手許を離れ、神ならぬ神々を拝むものとなった私達ですが、そうした神社仏閣は人間の宗教心が造り出した偶像に過ぎません。真の神様から離れている(的外れ)ことを“罪”と言います。
●愛の癒し
何処にも行先の無い一心は陸徳志の元に身を寄せますが、まもなく高熱を発症します。駆け付けた医者は「黒腋病」と診断、高価な薬を処方するしか無い、と云うが、それは陸徳志の財力を遥かに超えるものだった。思案に暮れる徳志に妻、淑琴が提案する。「元日本人街のどこかへおいて来たらまだ残っている日本人が拾って、助けてくれるでしょう」。辛いながらも、そうするしか一心は助からないと思えた。早速、荷車を借りてきた陸徳志は一心を乗せ、曾て日本の管理下にあった満州電信電話会社傍の空家に布にくるんだ一心を置いた。「お前の強運を祈るよ、七台屯から長春まで千六百里(八百キロ)を一人で生き延びたお前だ。日本人に拾われて、日本のいい薬で癒して貰うんだよ」。徳志は心を鬼にしてそこを離れると、目前に数匹の野犬が襲いかかって来た。石を投げつけて難を逃れたが、俄かに残してきた一心の身が案じられた。「何という人の道にはずれたことを」と、息を切らせて元の空家に辿り着くと中から声がする。「先生……、おいて行かんで……」。高熱で動けないはずの一心が布団から這い出していた。徳志は思わず一心を抱きかかえた。熱いものがこみ上げて来た。もとの荷車に乗せて、家へ向かって車を曳いた。
その翌日から徳志は小学校へ出勤する以外のすべての時間を一心の看病に充てた。医者や高額薬に頼ることは叶わないが、人づてに聞く良薬を呑ませ淑琴と交代で看病した。彼らの“愛”が奏功したのか、一ヵ月ほどで黒い血は止まり、体力も徐々に回復して来た。淑琴は粥を作って、寝ている一心に食べさせ、精がつくからと、卵も与えた。一心を見る眼が次第に温かくなった。そんな或る日、淑琴は、「元気になっても、この子を手離すのかと思うと淋しいですねぇ、いっそ、うちの子にしては」と話す声が寝ている一心の耳に聞こえた。
徳志は、「お前がそう思うのなら、うちの子供にしよう、何事も誠意で行うという意味で、陸一心という名にしよう」と云い、「今日から私のことを父さん、淑琴のことを母さんと呼ぶんだよ」と告げると、八歳の一心は、こくりと頷いた。しかしこの言葉が一心の口から出るまでには、もう少し時間を要した。
「高価な薬が必要」なはずの難病も、養父母の身を削る看病で治りました。実は私達の身体には免疫力、自己治癒力が備わっていますがそうした本来の力を活性化させる要因として、人の注ぐ愛や明日への希望が大きく関わっているようですね。
●内から出る力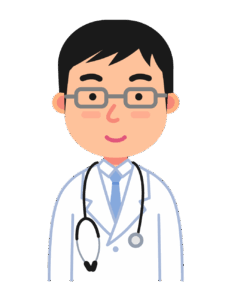
医学の進歩や医療インフラの充実で私達の寿命も随分と延び、「100歳まで」が戯言から現実味を帯びた言葉へと変わりつつあります。それでも“不治の病”を“死語”へと追いやることは出来ませんね。医者も「お手上げ」の病気に罹患した人の話を聖書から紹介しましょう。
「ところで、十二年の間長血をわずらている女がいた。この女は多くの医者からひどいめに会わされて、自分の持ち物をみな使い果たしてしまったが、何のかいもなく、かえって悪くなる一方であった。彼女は、イエスのことを耳にして、群集の中に紛れ込み、うしろから、イエスの着物にさわった。『お着物にさわることでもできれば、きっと直る』と考えていたからである。すると、すぐに、血の源がかれて、ひどい痛みが直ったことを、からだに感じた。イエスも、すぐに、自分のうちから力が外に出て行ったことに気づいて、群集の中を振り向いて、『だれがわたしの着物にさわったのですか』と言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。『群集があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも『だれがわたしにさわったのか』とおっしゃるのですか。
イエスは、それをした人を知ろうとして、見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こった事を知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこで、イエスは彼女にこう言われた。『娘よ。あなたの信仰があなたを直したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、すこやかでいなさい』」(マルコ5章25節~34節)。
病魔に、心身も財産もボロボロになった女性。当時の「ゴッド ハンド」を探し続けましたが、どの名声も評判倒れでした。諦めかけていた折、耳にしたのがイエスの噂。群衆に紛れ、後ろから着物に触れると、一瞬に完治したのです。医者ではありません。薬でもありません。私達の体を癒すのは人体も心もお造りになった神、神の愛が発動して癒されるのです。弟子達は言いました。「群衆があなたに押し迫っている」と。誰かが触れたとしてそれに気付くのは不可能、ましてその部分が「着物」なら尚更。しかし、イエスは気付きました。「この群衆の中にわたしの愛を必要としている女性がいる」。街中の防犯カメラが人々の行動を監視する時代、犯人の検挙もスピードが増しています。しかし、弱者、心のSOS、声にならない呼びを聴く“愛のカメラ”もまた現代社会に必要とされるアイテムではないでしょうか。今、キリストの眼差しがあなたにも注がれているのです。
●お父さん
漸く落ち着ける場を得た一心でしたが、それも束の間、国民党と共産党との内戦が激化してきました。戦乱を避けようと徳志は妻と一心を伴って長春の家を出ました。やがて国民党の兵隊が立つ検問所に至ります。「親子三人だな、ここを出ると、もう二度と長春市には戻れないぞ、いいか」と念を押されつつ通過は許可された。一キロ程の荒涼とした土地を挟んだ向こう側に共産党の検問所がある。どうしたことか、多くの避難民がこの緩衝地帯に押し込められている。食料事情の悪化で共産党が通行制限をしているらしい。となるとこの袋小路、互いが食料を奪い合う“生き地獄”と化すのは必至。新参者の陸家族も早速その餌食にされてしまった。淑琴が長旅の為にと備えた食料が一口も食べないうちに強奪されてしまったのだ。弱った者から順に倒れてゆく、そんな極限状態の果て、ようやく「検問所が開くぞ」と朗報が聞こえた。
群衆がわれ先にと殺到する中、一心が検問で止められた。「お前の中国語はおかしい、日本人か!」。一心が後ろにいないことに気付いた徳志は、押し寄せる人の流れに逆行し、柵門に駆け寄った。「その子は私の子供です、一緒に出して下さい」。強引に一心を連れ出そうとする徳志に兵隊が銃口を突きつけた。背後で淑琴の悲鳴が響く。異変に気付いた上級者らしい男が来た。兵隊から事情を聞くと、「あんたの実の子か、日本人の子か、正直に答えないと、ためにならん、どっちだ」と厳しい視線を向けた。
徳志は一瞬、ごくりと唾を呑むと覚悟を決めた。「あの子は、私のたった一人の息子です、十歳の子供が、あの地獄の中を生き抜いたのです、どうか生かしてやって下さい、その代わり私が中に戻ります」。上級者らしい男は呆然と立ち竦む少年と徳志を見比べ、銃を構える兵隊に命じる。「同志、あの柵の中へ戻れば餓死することが解かっていて、なお且つ、子供だけを助けようとすることはわれわれ共産党と解放軍の基本精神だ。受け入れよう」。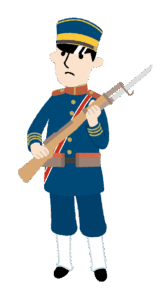
徳志と一心を阻んでいた銃剣が降ろされ、一心の体が柵の外へ押し出された。その瞬間、一心は狂ったように声を上げた。「お父さん!」。徳志の首にしがみつき、体をよじって泣いた。これまでどんなに懐(なつ)き、どのような状況の中でも口にしなかった「お父さん」という言葉が、はじめて一心の口をついて出た瞬間だった。
●アバ、父
量り知れない徳志の愛は知ってはいたが、それでも一心は“父”と呼べなかった。「その代わり私が中に戻ります」の言葉に、堪らず「お父さん」と呼んだ。実は一心には、生き別れになった実親がいたのだ。成人後、この実父とビジネスの世界で邂逅、やがて実父は日本への帰還を打診する。しかし一心は中国人であること、陸徳志の子であることを選ぶ。そう、彼はあの検問所、命を懸けて助けてくれた陸徳志を「お父さん」と決めたのだ。単に検問を逃れるための方便ではなく、本当の“父”としてそう叫んだのだ。それが一心の変わらぬ選択となったのです。さて聖書はこの血で繋がった両親とは別の“父”を私達に示しています。
「しかし、この方(キリスト)を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子どもとされる特権をお与えになった」(ヨハネ1:12~13)。
陸徳志の姿、それは私達の魂の親である神様の“写し鏡”のようです。徳志は「その代わり私が」と命を捨てる覚悟を示しましたが、キリストもまた私達の代わりに十字架に架かって下さったのです。何故でしょうか。徳志が一心を愛したように、キリストもまた私達を愛して下さったからです。この方を救い主と信じる時、私達は神を“父”と呼ぶことが出来るのです。使徒パウロは下記のように記しました。
「あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、『アバ、父』と呼びます」
(ローマ8:15)。


