第19回 空蝉(うつせみ)の声
空蝉(うつせみ)の声
●岩にしみ入る蝉の声
「海の日」、だというのに何故か深山渓谷を逍遥。山越え谷を渉った。もはや異郷というより異界でしょうか。この別世界では人工的な色彩、騒音が一切排除される。岩を叩く渓流の音、鳥の囀り。ふと耳を澄ませると、もう蜩(ヒグラシ)の啼き声。カナカナカナ、、、、が永く閉ざされた扉を拓く、そこからもう一つ別の声が耳を過る。
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声(芭蕉)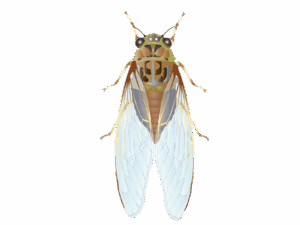
“蝉”ならば我が茅屋の周辺にも沢山居るが、その発する“音”は周囲に融け込まず空中を彷徨う。やがては雑音と消える。蝉に何の違いもないが、特定の空間に立った時、見えなかった景色が顕れ、聴こえなかった音が“声”となる。その“声”が心の糸を弾くのだろうか。遠かった俳聖との距離が少し縮まったような気がした。
●八日目の蝉
俳聖とは別にもう一人の作家の声も聞こえてきた。実話を基に紡がれた角田光代著「八日目の蝉」。不倫相手の子を妊娠、堕胎した女性、野々宮希和子が、正妻の産んだ乳児を誘拐し四年に亘る逃避行をする。物語の前半はこの逃避行に割かれる。戸籍、健康保険書すら持たない“薫”と名付けた女児を連れ、警察やマスコミの目を逃れながらも我が子のように育てる希和子の直向きさに、読者側も「頑張れ!」と応援してしまう。東京、名古屋、大阪と転々としながら最後にやって来たのは瀬戸内の小豆島。親切な島民に受け入れられ生活も落ち着き始める。そして夏。都会から隔絶された島民の楽しみは何かと託けて催される種々のお祭りだ。7月2日は「虫おくり」の祭事。親しくなった近隣家族に誘われて薫と共に出掛ける。夕闇にふわふわと揺れる灯明の中、フラッシュを具えたレンズが目が世間の凝視と重なる。「家族写真なのだろう」と言い聞かせながらも不安の火種は消えない。そしてその不安は的中する。たまたま地元のアマチュアカメラマンが撮ったスナップ写真が入選、全国紙に掲載されたのだ。あろうことか希和子と薫がはっきりと写っている。島民の歓喜とは裏腹に、追手の急迫を察知した希和子は薫の手をとり港へと急ぐ。しかし、その港が4年に亘る逃避行に終止符を打つ場所となった。
小説の後半はその後の薫の物語。薫は実親の元に、名前も本来の恵理菜に戻される。恵理菜は物心ついた頃から自分の過去を調べ始める。生後まもなく野々村希和子という女性に誘拐されたこと、そして四年余りの年月、その女性に育てられたこと。その後の裁判経緯、世間の誹謗中傷を含め様々な角度から俯瞰する。そして行き着いた結論は「野々宮希和子って何て馬鹿な女なんだ」ということだった。ところがこの恵理菜、自分もまた希和子と同じ道を歩んでいることに愕然とする。未だ大学生だというのに、不倫相手の子を宿してしまったのだ。そんなときに現れたのが千草と名乗る女性。二十年前の大阪、隠遁先の怪しい施設で一緒だったという女性だ。フリーライターの千草は「取材」という名目で恵理菜を過去を辿る旅へと誘い出す。千草は言う。「前に、死ねなかった蝉の話をしたの、あんた覚えてる?七日で死ぬよりも、八日目に生き残った蝉のほうがかなしいって、あんたは言ったよね。私もずっとそう思ってたけど」千草は静かに言葉をつなぐ。「それは違うかもね。八日目の蝉は、ほかの蝉には見られなかったものを見られるんだから。見たくないって思うかもしれないけど、でも、ぎゅっと目を閉じてなくちゃいけないほどにひどいものばかりでもないと、私は思うよ」。千草は気付いていたのだ。恵理菜が過去から目を背けていることを。
 さて、旅の終わり、恵里菜は小豆島へと向かう。17年前、希和子が逮捕された土庄港が視野に入る。刹那、希和子が最後に叫んだ声、その微かな声が封印を解かれた記憶の彼方から蘇り、恵里菜の耳朶を打つ。
さて、旅の終わり、恵里菜は小豆島へと向かう。17年前、希和子が逮捕された土庄港が視野に入る。刹那、希和子が最後に叫んだ声、その微かな声が封印を解かれた記憶の彼方から蘇り、恵里菜の耳朶を打つ。
「その子は朝ごはんをまだ食べていないの」
刑事の腕に抱えられながら連れて行かれる自分、その私にすがるように伸ばされた手、絶望に圧し潰された涙目、すべての光景が瞼裏に蘇る。
「その子は朝ごはんをまだ食べていないの」、その声が、岩のように硬かった自分の頭蓋骨にしみ入る。これで終わり、という時に希和子が心配していたのは薫(恵理菜)の空腹だけだったのだ。その時、薫ははっきりと八日目の光景を正視する。「野々村希和子は私の母親だった」と。恵理菜はいつも思っていた。野々宮希和子、なんて馬鹿な女なんだ。何故、そんな馬鹿なことをしたんだって。しかし、彼女の愚行は全て私の為、私を愛し、私を護ろうとして馬鹿になった。合理的な理解では説明出来ない、目には見えない“愛”が聞こえた瞬間となったのです。
●ゴルゴダからの声
親なればこそ、我が子を庇う。恵理菜が希和子と引き離されたその港で、希和子の母性に気付いたように、私達は十字架という極刑の現場で、魂の親キリストに出会います。
「そのとき、イエスはこう言われた。『父よ、彼らをお赦しください。彼らは、自分が何をしているのかが分かっていないのです。』」(ルカ23章34節)。
最近、朝刊紙面で「過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪」を、という被害者親族側の主張が目に留まりました。「38度の高熱状態で睡眠を誘発する風邪薬を服用後、運転、ブレーキも踏まずに衝突、何故これが過失なのか!」。重刑を求める被害者側の怒りは尤もです。ところが十字架の場面、普通とは真逆の懇願がイエスの口から放たれたのです。「彼らをお赦しください」。何故なら、「自分が何をしているのかが分かっていない」、つまりこれ(彼らがキリストを磔刑にしたこと)は過失だ、と。
この言葉は多くの人々、その岩の心に染み入りました。その最初の人物はイエスと共に十字架に架けられた犯罪人だったのです。
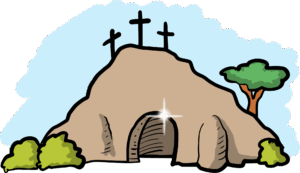 「十字架にかけられていた犯罪人のひとりはイエスに悪口を言い、『あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え』と言った。ところが、もうひとりのほうが答えて、彼をたしなめて言った。『おまえは神をも恐れないのか。おまえも同じ刑罰を受けているではないか。われわれは、自分のしたことの報いを受けているのだからあたりまえだ。だがこの方は、悪いことは何もしなかったのだ。』そして言った。『イエスさま。あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。』イエスは、彼に言われた。『まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます。』」(ルカ23章39節~43節)。
「十字架にかけられていた犯罪人のひとりはイエスに悪口を言い、『あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え』と言った。ところが、もうひとりのほうが答えて、彼をたしなめて言った。『おまえは神をも恐れないのか。おまえも同じ刑罰を受けているではないか。われわれは、自分のしたことの報いを受けているのだからあたりまえだ。だがこの方は、悪いことは何もしなかったのだ。』そして言った。『イエスさま。あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。』イエスは、彼に言われた。『まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます。』」(ルカ23章39節~43節)。
その生涯、何も良いことは無く、挙句の果てに人を殺め極刑に。そのような男が、初めて自分の非を認めたのです。「自分のしたことの報いを受けている」と。何がこの男を変えたのでしょうか。そう、彼の頑なな心はイエスの言葉に溶かされたのです。
「彼らをお赦しください」
耳から入った言葉は頭へ、そして心に浸潤しました。自分が罪人だと悟ったとき、景色は一変しました。残酷な刑場が天国への入り口へと、雑音にすら思えた「彼らをお赦しください」が意味を持った“声”、キリストの赦しの宣言へと変わったのです。すべてが腑に落ちた瞬間です。そしてこの景色はゴルゴダ(十字架刑場)から、換言しますと自分こそが裁かれるべき罪人だと自覚した丘に立たない限り見えてこない、聴こえてこない景色なのです。
●八日目の景色
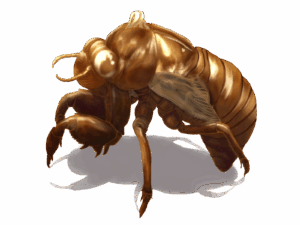 “蝉”と言えばどうしても頭に遡上してくるキャラクターがあります。“空蝉(うつせみ)”、という綽名を付けられた女性、そう「源氏物語」です。空蝉とは元々、蝉の抜け殻を意味する言葉ですが、この女性は源氏の執拗なアプローチを徹底的に拒否するのです。寝間に忍び込んだ源氏に脱ぎ捨てた上着だけを掴ませて逃げる、大したものです。それで彼女は“空蝉”と呼ばれるようになりました。
“蝉”と言えばどうしても頭に遡上してくるキャラクターがあります。“空蝉(うつせみ)”、という綽名を付けられた女性、そう「源氏物語」です。空蝉とは元々、蝉の抜け殻を意味する言葉ですが、この女性は源氏の執拗なアプローチを徹底的に拒否するのです。寝間に忍び込んだ源氏に脱ぎ捨てた上着だけを掴ませて逃げる、大したものです。それで彼女は“空蝉”と呼ばれるようになりました。
さて、実は聖書では八日目というのはある意味を示唆する言葉でもあります。一週間は日曜日から始まるので、次週の日曜日は八日目になります。AD30年4月、イエス・キリストがエルサレムに入場した日曜日から数えて六日目が十字架、そして八日目の朝、その出来事は起こりました。
「さて、週の初めの日に、マグダラのマリヤは、朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして、墓から石が取りのけてあるのを見た。それで、走って、シモン・ペテロと、イエスが愛された、もうひとりの弟子とのところに来て、言った。『だれかが墓から主を取って行きました。主をどこに置いたのか、私たちにはわかりません。』そこでペテロともうひとりの弟子は外に出て来て、墓のほうへ行った。ふたりはいっしょに走ったが、もうひとりの弟子がペテロよりも速かったので、先に墓に着いた。そして、からだをかがめてのぞき込み、亜麻布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いて来て、墓に入り、亜麻布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは、亜麻布といっしょにはなく、離れた所に巻かれたままになっているのを見た。そのとき、先に着いたもうひとりの弟子も入って来た。そして、見て、信じた。彼らは、イエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書を、まだ理解していなかったのである。それで、弟子たちはまた自分のところに帰って行った。しかし、マリヤは外で墓のところにたたずんで泣いていた。そして、泣きながら、からだをかがめて墓の中をのぞき込んだ。 すると、ふたりの御使いが、イエスのからだが置かれていた場所に、ひとりは頭のところに、ひとりは足のところに、白い衣をまとってすわっているのが見えた。彼らは彼女に言った。『なぜ泣いているのですか。』彼女は言った。『だれかが私の主を取って行きました。どこに置いたのか、私にはわからないのです。』彼女はこう言ってから、うしろを振り向いた。すると、イエスが立っておられるのを見た。しかし、彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。『なぜ泣いているのですか。だれを捜しているのですか。』彼女は、それを園の管理者だと思って言った。『あなたが、あの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。』イエスは彼女に言われた。『マリヤ。』彼女は振り向いて、ヘブル語で『ラボニ(すなわち、先生)』とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。『わたしにすがりついてはいけません。わたしはまだ父のもとに上っていないからです。わたしの兄弟たちのところに行って、彼らに『わたしは、わたしの父またあなたがたの父、わたしの神またあなたがたの神のもとに上る』と告げなさい。』マグダラのマリヤは、行って、『私は主にお目にかかりました』と言い、また、主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。」(ヨハネ20章1節~18節)
すると、ふたりの御使いが、イエスのからだが置かれていた場所に、ひとりは頭のところに、ひとりは足のところに、白い衣をまとってすわっているのが見えた。彼らは彼女に言った。『なぜ泣いているのですか。』彼女は言った。『だれかが私の主を取って行きました。どこに置いたのか、私にはわからないのです。』彼女はこう言ってから、うしろを振り向いた。すると、イエスが立っておられるのを見た。しかし、彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。『なぜ泣いているのですか。だれを捜しているのですか。』彼女は、それを園の管理者だと思って言った。『あなたが、あの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。』イエスは彼女に言われた。『マリヤ。』彼女は振り向いて、ヘブル語で『ラボニ(すなわち、先生)』とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。『わたしにすがりついてはいけません。わたしはまだ父のもとに上っていないからです。わたしの兄弟たちのところに行って、彼らに『わたしは、わたしの父またあなたがたの父、わたしの神またあなたがたの神のもとに上る』と告げなさい。』マグダラのマリヤは、行って、『私は主にお目にかかりました』と言い、また、主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。」(ヨハネ20章1節~18節)
その日の早朝、マリヤはイエスの葬られた墓へと急ぎました。しかし彼女を待っていたのは「亜麻布と布切れ」、まさに“抜け殻”でした。一報を受けた弟子ペテロ、ヨハネも駆けつけましたが、空となった墓に困惑しつつもそこを立ち去りました。しかし、そこに留まり続けたマリヤを“異界”が覆いました。「マリヤ」と語り掛ける声が聞こえたのです。
●空墓からのメッセージ
残念なことに、「処女降誕」や「復活」を語らない、或いは歴史的事実として認めない“キリスト教”が席巻しているようです。非科学的と思える“奇跡”が世間に受け入れられないのは確かにその通りでしょう。しかし、この「空になった墓」に立たない限り、キリストの語り掛けは聞こえてきません。“永遠の命”も“天国”も全て絵空事、観念の世界へと閉じ込めてしまうのです。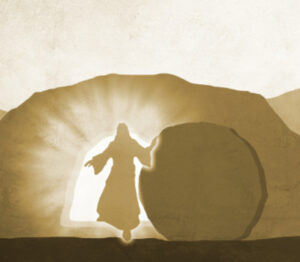
皆さんの中に教会に通い始めた、或いは聖書を読み始めた方はいらっしゃいますか。是非、キリストの十字架、そして復活を都合よく理解するのではなく、対峙して下さい。真剣に向き合って下さい。十字架の現場に立ち続けたローマの百人隊長は最後にこう言ったのです。
「この方は本当に神の子であった」(マルコ15章39節)。
この拙文を読んで下さった方が、上記、同じ告白をされることを願っております。


