第21回 自分への死刑判決
自分への死刑判決
●虚飾の観光地
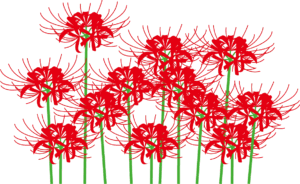 車窓から飛込んで来る一面の“赤絨毯”に「ん?」、目が奪われた。「なんだ、彼岸花か」。長かった酷暑も漸く背を向けてくれた。となると今度は全身を被う“赤の天蓋”が待ち遠しい。そう紅葉だ。あと一ヵ月程だろうか。今や“紅葉”も観光資源らしい。三年間通った高校の傍らに「永観堂」(京都市左京区)という古刹がある。今や古都でも屈指の集客を誇る紅葉の名所らしい。「鹿ケ谷の陰謀」と言えば、「あっ、あの辺りか」と首肯される方もおられよう。銀閣寺と南禅寺を結ぶ「鹿ケ谷通り」は哲学の道とも重なり、今や多くの外国人がその人工的な“自然”に誘(おび)き寄せられ優雅に舞う。
車窓から飛込んで来る一面の“赤絨毯”に「ん?」、目が奪われた。「なんだ、彼岸花か」。長かった酷暑も漸く背を向けてくれた。となると今度は全身を被う“赤の天蓋”が待ち遠しい。そう紅葉だ。あと一ヵ月程だろうか。今や“紅葉”も観光資源らしい。三年間通った高校の傍らに「永観堂」(京都市左京区)という古刹がある。今や古都でも屈指の集客を誇る紅葉の名所らしい。「鹿ケ谷の陰謀」と言えば、「あっ、あの辺りか」と首肯される方もおられよう。銀閣寺と南禅寺を結ぶ「鹿ケ谷通り」は哲学の道とも重なり、今や多くの外国人がその人工的な“自然”に誘(おび)き寄せられ優雅に舞う。
さて、この雅を装う鹿ケ谷、実は平家掃討の発火点ともなった悍ましい旧跡でもあるのです。1177年、首謀者は俊寛僧都、黒幕は後白河法王。ところが歴史の常、密告により平清盛に知れてしまい、後白河法王は幽閉、俊寛僧都は鬼界ヶ島(現、「喜界ヶ島」と推定)への流罪で一件落着。傍目には平家打倒の芽は潰えたかのように見えた。
●以仁王の蜂起と幻想
 しかし、その火種は僅かな酸素を吸引しながら地中に燻っていた。三年後の1180年「以仁王の令旨」の発布が世間を震撼させた。否応なく源平合戦の口火が切られるが、圧倒的な平家の軍勢の前に反乱軍は雲散霧消。興味深いのは、何故この無謀な蜂起に聡明との評価が高い以仁王(後白河天皇の第三皇子)が乗ったか、です。一つには、前述の俊寛僧都から受けた“火種”が有ります。彼等は例の鹿ケ谷で顔を合わせています。そしてもう一つは、以仁王に“夢を売った男”源頼政の巧言です。「今、以仁王が令旨を発すれば平家を憚って雌伏している源氏の一族が必ずや蜂起して平家を倒すにちがいない。老いたりと雖も、まず私が子供を引き連れて味方に参上する」と。戦力を分析すれば、勝算は希薄。しかし彼の甘言は以仁王に過去に聞いた「託宣」を呼び覚ました。「人相見の少納言」と云われた藤原維長はかつて以仁王に「あなたは天皇になる人相を備えておいでだ」と言ったのだ。「これだ、繋がった!」。この訝言が以仁王の心を鷲掴みにした。しかし戦いが始まると数に劣る源氏勢は敗走。頼政は宇治平等院で自害(「扇の芝」)、以仁王も南都へ逃れる途上、平家の追手に射止められた。
しかし、その火種は僅かな酸素を吸引しながら地中に燻っていた。三年後の1180年「以仁王の令旨」の発布が世間を震撼させた。否応なく源平合戦の口火が切られるが、圧倒的な平家の軍勢の前に反乱軍は雲散霧消。興味深いのは、何故この無謀な蜂起に聡明との評価が高い以仁王(後白河天皇の第三皇子)が乗ったか、です。一つには、前述の俊寛僧都から受けた“火種”が有ります。彼等は例の鹿ケ谷で顔を合わせています。そしてもう一つは、以仁王に“夢を売った男”源頼政の巧言です。「今、以仁王が令旨を発すれば平家を憚って雌伏している源氏の一族が必ずや蜂起して平家を倒すにちがいない。老いたりと雖も、まず私が子供を引き連れて味方に参上する」と。戦力を分析すれば、勝算は希薄。しかし彼の甘言は以仁王に過去に聞いた「託宣」を呼び覚ました。「人相見の少納言」と云われた藤原維長はかつて以仁王に「あなたは天皇になる人相を備えておいでだ」と言ったのだ。「これだ、繋がった!」。この訝言が以仁王の心を鷲掴みにした。しかし戦いが始まると数に劣る源氏勢は敗走。頼政は宇治平等院で自害(「扇の芝」)、以仁王も南都へ逃れる途上、平家の追手に射止められた。
ところが、この「以仁王の令旨」が後の源頼朝、木曽義仲による平家打倒への葉脈となったのだから歴史は繋がっている。平家討伐は謀反ではなく正義である、との大義名分を勝ち得たからである。
●心中の激闘
「あなたは天皇になる人相」から想起させられるのがシェークスピアの「マクベス」。物語の冒頭に登場する魔女が放った一言、「マクベス殿!いずれ王となられるお方!」が勇将マクベスの心を射抜く。「現王を押し退けてこの俺が王に、馬鹿な!」と一蹴する理性と、その理性を哄笑する“野望”が相克。最初は小さな火種に過ぎなかった野望が、癌細胞のように周囲を浸潤し、心中に流血の闘いを繰り広げる。外敵との幾多の戦いを制してきた猛将マクベスも内側の“心”を制することに満身創痍となる。
この心中の葛藤に付き、キリスト者である使徒パウロは「私のうちに住んでいる罪」(ローマ7章17節)と表現しました。「住む」という動詞が充てられたことに要注目です。通常、「住む」という単語は生物に使われます。パウロは「罪」を生き物、と捉えたのです。
●勝利は何方へ
千歳一隅の報がマクベスの許に届いた。王ダンカンがマクベスの居城を来訪する、というのだ。これは吉報、それとも凶報?。「この機会に王を殺せば、自分が代わって、、、」。あろうことか夫人までもが嗾(けしか)ける。「一生をだらだらとお過ごしになるおつもり?」。マクベスは七転八倒の悶絶、理性は叫ぶ。「お願いだ、黙っていてくれ、男にふさわしいことなら、何でもやってのけよう、それも度が過ぎれば、もう男ではない、人間ではない」。しかしこの絶叫、理性が発した「断末魔」となった。“罪”に惨殺されたのだ。
●主従逆転
「罪を行っている者はみな、罪の奴隷です」(ヨハネ8章34節)とキリストは語る。マクベスは何故、理性を勝利へと導けなかったのか。それは丁度、主人と奴隷の関係と同じだとキリストは説明する。私達は“罪”を犯すか否かは自分の手中にある、と考えます。しかし聖書は言います。罪が主人、人はその奴隷だ、と。“依存症”に似ていますね。アルコール依存症、ギャンブル依存症、様々な“依存症”がありますが、本人は「自分で制御出来る」と誤診している点が共通しています。現実は、当人は殆ど無抵抗です。奴隷は主人に逆らえません。同様、人は罪の命令に逆らえない、と聖書は教えています。
●死の真因
 ダンカン王を暗殺したマクベスは、その罪を王の従者に着せ、さらに“成敗”という名目で口封じをします。罪を隠匿する為に次々と際限なく無辜の血を流す殺人鬼へと変貌、最後には自分も命を奪われ閉幕となります。
ダンカン王を暗殺したマクベスは、その罪を王の従者に着せ、さらに“成敗”という名目で口封じをします。罪を隠匿する為に次々と際限なく無辜の血を流す殺人鬼へと変貌、最後には自分も命を奪われ閉幕となります。
さて、「罪の報酬は死です」(ローマ6章23節)と聖書は言います。かつて「不治の病」と恐れられた天然痘や結核は医学の進歩によって治癒が可能となりました。今後、“癌”も駆逐出来るかも知れませんね。しかし、それでも“死”を克服することは出来ません。“死”は「罪の報酬」だからです。
●自分への死刑判決
シュークスピア作品、誰もが共感出来る人間の矛盾と脆弱さが、多くの人々を魅了するのでしょう。そして聖書にも善悪という相容れぬ両極の深淵に溺れる哀れな人物が多く登場します。今回は紀元前年頃のイスラエルの王ダビデを紹介しましょう。
主がナタンをダビデのところに遣わされたので、彼はダビデのところに来て言った。「ある町にふたりの人がいました。ひとりは富んでいる人、ひとりは貧しい人でした。」富んでいる人には、非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は、自分で買って来て育てた一頭の小さな雌の子羊のほかは、何ももっていませんでした。子羊は彼とその子どもたちといっしょに暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼のふところでやすみ、まるで彼の娘のようでした。あるとき、富んでいる人のところにひとりの旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人の雌の子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。」すると、ダビデは、その男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。「主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は、あわれみの心もなく、そんなことをしたのだから、その雌の子羊を四倍にして償わなければならない。」ナタンはダビデに言った。「あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう仰せられる。『わたしはあなたに油をそそいで、イスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらに、あなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたのふところに渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、わたしはあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主のことばをさげすみ、わたしの目の前で悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリヤを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今は剣は、いつまでもあなたの家から離れない。あなたがわたしをさげすみ、ヘテ人ウリヤの妻を取り、自分の妻にしたからである。』主はこう仰せられる。『聞け。わたしはあなたの家の中から、あなたの上にわざわいを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は、白昼公然と、あなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れて、それをしたが、わたしはイスラエル全部の前で、太陽の前で、このことを行おう。』」ダビデはナタンに言った。「私は主に対して罪を犯した。」ナタンはダビデに言った。「主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。(Ⅱサムエル12章1節~13節)。
神はダビデに自らの罪を気付かせようと預言者ナタンを遣わされました。彼はダビデにある例話をしますが、聞いたダビデはその非道な男に激怒し、「死刑だ」と糾弾しますが、振り上げた斧は、己が頭上に振り下ろされる“死刑判決”へと変わりました。実はダビデは美しい夫人との情事に溺れますが、その女性の懐妊を知ると、その罪を隠そうと夫を作為的に戦死させます。ダビデは正義を尊ぶ王ですが、その道徳観とは真逆の大罪を犯してしまったのです。マクベスと同様、彼もまた“矛盾”を孕んだ人物なのです。さて、このダビデはマクベスと違って歴史上実在の人物です。ミケランジェロ^が作品のモデルとし、今なおイスラエルの民が憧憬する理想像なのです。何故、かくも醜い人物が天才芸術家のモデルとなり、ある民族のとっての理想なのでしょうか。それはダビデの最後の一言にあります。「私は主に対して罪を犯した」(13節)がそれです。
●認罪と赦し
実は、簡単そうで限りなく困難なこと、それが自分の罪を素直に認めることではないでしょうか。「間違っていました、赦して下さい」。こんな簡単な一言が何故言えないのか、と他者事なら客観的視するのに、我が事となると「いや、私は、、、」と最後まで抵抗するのは何故でしょう。理想の王ダビデ、下命一つでナタンの口を封殺することも出来た彼がそれをせず、非を認めたからこそ高く評価されるのではないでしょうか。
そしてナタン、「主もまた、あなたの罪を見過ごしてくださった」(13節)。「えっ、そんな馬鹿な」と憤怒されるかも知れません。“死刑だ”、という全うな判決が何故、“逆転”無罪になるのか。実はこの正反対の出来事が歴史を塗り替えました。そうAD30年です。無罪であるはずの神の御子イエスが“死刑”とされたのです。これは“身代わり”です。
人間の創る法律でも“一事不再理”という原則があります。一度確定した判決に付き、同じ罪で二度責任を科せられることは無い、というものです。この原則はキリストによる贖罪にも適用されます。イエスが“身代わり”である以上、罪人は裁かれない、ということです。ではその“裁かれない者”とは誰なのでしょうか。
●一人として例外はない
「神は、実にそのひとり子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠のいのちを持つためである」(ヨハネ3章16節)。
神は“世”を、すなわちこの世に生きる全ての者を愛されました。換言すると全ての人が“身代わり”の対象です。しかし、その効力を頂いて“無罪”とされるのは、「御子を信じる者」になります。ダビデのように「私は主に対して罪を犯した」と告白する者です。罪の自覚が無ければ、御子イエスが自分の罪の身代わりとなって下さった、という福音の真理が分かりません、つまり御子を主として信じる(身代わりの贖い主として)ことが出来ないのです。この理解を欠いた“信仰告白”は空疎な朗読に過ぎません。ダビデは罪を告白しましたので、千年後のイエスの身代わりで赦されました。そしてその効力は今の私達にも有効なのです。
罪を告白したダビデは自分の心情を聖書の別の箇所でこのように記しました。
「神へのいけにえは、砕かれた霊。砕かれた、悔いた心。神よ。あなたは、それをさげすまれません」(詩篇51篇)。
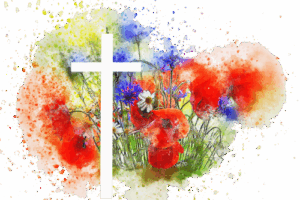
イエスは言われました。
「わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて、悔い改めさせるために来たのです。」(ルカ5章32節)。
是非、この招きを受ける方となって下さい。


