No.07 食品サンプル|道しるべ
 「なに、この店?」。足を踏み入れて思わず立ち止まった。昨年、郡上八幡へ小旅行に出掛けた時のこと。店内の至る所に置かれた“あるモノ”に目が吸い寄せられる。それは私達が普段レストランの店先で目にするアレ、そう、食品サンプルでした。郡上八幡は国内随一の生産数を誇る食品サンプルの町でもあったのです。
「なに、この店?」。足を踏み入れて思わず立ち止まった。昨年、郡上八幡へ小旅行に出掛けた時のこと。店内の至る所に置かれた“あるモノ”に目が吸い寄せられる。それは私達が普段レストランの店先で目にするアレ、そう、食品サンプルでした。郡上八幡は国内随一の生産数を誇る食品サンプルの町でもあったのです。
初めてのレストランって期待度高いですよね。さて、何を注文しようか。決め手になるのは、矢張り店先の食品サンプルでしょう。“お品書き”の「〇〇うどん」だけではボリューム感や具材の種類、麺の細太が何一つ伝わって来ません。何よりも食欲をそそる「美味しそうっ!」感が漂いません。テーブルで待つ間の高揚感、これもまたサンプルの効用でしょう。 ところが、である。「は~い、お待たせ~っ」と目の前に置かれた一品に「ん?」、目を疑ったことは有りませんか。「これ僕が頼んだやつ?、本当?、サンプルと随分違う」と顔を曇らせた経験。「サンプルに“偽り”有り」と糾弾したくなりますよね。でもちょっと待って下さい、肝心なのは“味”じゃないですか。食べてみたら「美味しい!」と目が輝くかも知れませんよ。勿論、失望の増幅に終わることも。何れにせよ実際に食べるまでは先走った裁断はしてはいけませんね。
ところが、である。「は~い、お待たせ~っ」と目の前に置かれた一品に「ん?」、目を疑ったことは有りませんか。「これ僕が頼んだやつ?、本当?、サンプルと随分違う」と顔を曇らせた経験。「サンプルに“偽り”有り」と糾弾したくなりますよね。でもちょっと待って下さい、肝心なのは“味”じゃないですか。食べてみたら「美味しい!」と目が輝くかも知れませんよ。勿論、失望の増幅に終わることも。何れにせよ実際に食べるまでは先走った裁断はしてはいけませんね。
さて、聖書の中にも“事前情報”と“実際”との落差に驚嘆した人物がいました。「シェバの女王」です。「えっ、あのポールモーリアの」と頷く方もおられるかも知れません。そう、その同楽団の演奏で一躍有名になった楽曲名ですが、実は聖書に登場する実在の女王なのです。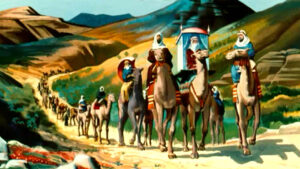 彼女が統治した紀元前10世紀、イスラエルはソロモンが王様の時代でした。女王はソロモンの名声を聞き及び、その真偽を見定めようとやってきたのですが、実際にソロモンに会ってその驚きを隠せませんでした。
彼女が統治した紀元前10世紀、イスラエルはソロモンが王様の時代でした。女王はソロモンの名声を聞き及び、その真偽を見定めようとやってきたのですが、実際にソロモンに会ってその驚きを隠せませんでした。
「私が国であなたの事績とあなたの知恵について聞き及んでいたことは、本当でした。私は自分で来て、自分の目で見るまでは、そのことを信じなかったのですが、なんと、私にはその半分も知らされてはいなかったのです。あなたの知恵と繁栄は、私が聞いていたうわさより、はるかにまさっています」(Ⅰ列王記10章6~7節)。
国の為政者として彼女は使者を派遣、場合によってはスパイを忍ばせたかも知れません。そして彼らは自らの見聞をそのまま王女に伝えますが、その報告があまりに超現実的で、「有り得ない」と信じなかったのです。しかし皆が同じことを言うので、「ならば」と自分で確かめにやって来たのです。ところが実際に自分の目で見、耳で聞くと、既知の内容を遥かに凌駕するものだったのです。「百聞は一見に如かず」をそのまま体験しました。これは食品サンプルとは真逆、情報よりも素晴らしかった例です。
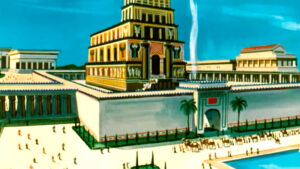 さてソロモンといえば「ソロモンの栄華」という言葉で知られるように、その並々ならぬ豪奢で有名です。今、NHKで「豊臣兄弟!」が放映中ですが、「秀吉のような」と形容すれば想像出来るでしょうか。天賦の知恵、途方もない財力と貿易、豪華絢爛な建造物と種々の器。秀吉は大阪城や聚楽第を建造しましたが、ソロモンも神殿、王宮を建てました。何れも金銀財宝が惜しみなく使われています。空前絶後の栄華を極めたソロモン王ですが、後の時代に「ソロモンに優る」と豪語する者が現れました。彼は言いました。
さてソロモンといえば「ソロモンの栄華」という言葉で知られるように、その並々ならぬ豪奢で有名です。今、NHKで「豊臣兄弟!」が放映中ですが、「秀吉のような」と形容すれば想像出来るでしょうか。天賦の知恵、途方もない財力と貿易、豪華絢爛な建造物と種々の器。秀吉は大阪城や聚楽第を建造しましたが、ソロモンも神殿、王宮を建てました。何れも金銀財宝が惜しみなく使われています。空前絶後の栄華を極めたソロモン王ですが、後の時代に「ソロモンに優る」と豪語する者が現れました。彼は言いました。
「南の女王(シェバの女王)が、さばきのときにこの時代の人々とともに立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい。ここにソロモンにまさるものがあります」(マタイの福音書12章42節)。
なんと、それを言ったのはイエス・キリストでした。さてこの方(イエス・キリスト)について皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。ユダヤ人、キリスト教の開祖、愛を説いた宗教家、様々な情報をお持ちでしょう。でもそれらは後代の人々によって糊塗された虚像かも知れません。控え目に言っても断片に過ぎません。虚実混交の情報が飛び交う現在、私達はソファに寝転び、お茶を啜りながら“空っぽの知識人”になることも可能です。しかしキリスト自身、そうした空疎な知識を戒めるかのようにこう語られたのです。「ソロモンの知恵を聞くために地の果てからやってきたシェバの女王」と。自国で得られる情報に満足せず、長旅を厭わなかった彼女を高く評価されたのです。
レストランのメニュー同様、矢張り自分の目で見、自分の舌で味わうことが本物を知ることの唯一の近道です。イエス・キリストに関する様々な情報は溢れていますが、肝心なのは自分で聖書を読むこと。食べて味わうように、キリストを知ることです。
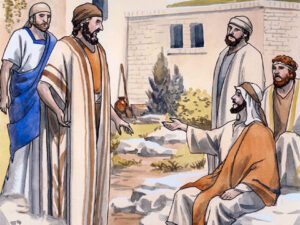 実はキリストの最初の弟子群、12使徒の中にも偏見を持つ者がいました。ナタナエルという人です。彼は知人のピリポからイエスの話を聞き反発しました。「ナザレから何か良いものが出るだろうか」と。見たことも会ったこともない人を、「ナザレ出身」という理由だけで蔑んだのです。
実はキリストの最初の弟子群、12使徒の中にも偏見を持つ者がいました。ナタナエルという人です。彼は知人のピリポからイエスの話を聞き反発しました。「ナザレから何か良いものが出るだろうか」と。見たことも会ったこともない人を、「ナザレ出身」という理由だけで蔑んだのです。
しかしピリポは言いました。「来て、見なさい」と。ナタナエルは言われた通りにしました。そして初対面のはずのイエスが自分以外に知り得ない自分の姿を言い当てたことに驚嘆しました。そして言ったのです。「先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です」。
皆さんも自分で聖書をお読みになり、また集会にお越しになりませんか。その時、皆さんも「ソロモンにまさる」と語られたキリストの外観上ではない、内側から出る“栄華”を味わうことが出来るでしょう。心からお勧めします。